自筆証書・公正証書遺言
自筆証書・公正証書遺言
1.遺言のすすめ
相続には、様々なトラブルがつきものですが、事前に回避できるものも少なくありません。しかし、ほとんどの方々は、「自分(の家族)は大丈夫だろう。自分はまだ元気だから・・・」と思って準備をしなかったり、問題になることを承知していたにもかかわらず、先延ばしにしてしまっていた結果、手遅れになってしまったというケースが大変多く見られます。
こんなケースは要注意!
- 子供がいないご夫婦。
- 相続人の中に判断能力を欠く方がいる。
- 相続人の中に行方不明者がいる。
- 複数の子供がいて、子供の一人が親名義の不動産に同居していて、その不動産以外には、ほとんど財産がない。
- 認知している子(いわゆる隠し子)がいる。
- 前妻又は前夫との間に子がいる(半血の兄弟がいる)。

これらのケースでは、遺産分割協議がすぐにできなかったり、事実上分割することができない等の難しい問題が潜んでいます。
また、そもそも相続権がない等下記のようなケースでは、遺言を準備しておかないと対応ができません。
- 法律婚をしていない(内縁関係)。
- 相続させたくない相続人がいる。
- 同居している長男の配偶者に長年介護してもらったので、遺産をあげたい。
様々な問題について、一義的に解決することはできませんが、まず、一番簡単かつ効果が高いと考えられるものに「遺言を書くこと」があげられます。
遺言は民法上、いくつかの形式が定められています。確かに「法律の形式上有効か」ということは重要な点であることに違いありませんが、形式上の問題よりも「その内容がどうなのか」という点も重要であることは、いうまでもありません。
2.自筆証書遺言
いつでもどこでも自由に作成できるのが自筆証書遺言です。思い立ったときにすぐ作成ができるという点では、非常に手軽な遺言です。全文自筆で記載し、日付、遺言者の氏名もすべて自筆で記載する必要があります。そのうえで押印して完成となります。
しかし、次のようなトラブルが多いのも事実です。
- 遺言書の形式的な要件を満たしておらず、法律的な効果が発生しない
- 遺産の分配について明確にされていなかったり、遺産が特定できない
- 字が読めない
- どこの誰にあげたいのか、受遺者が特定できない
- 一部の財産についてしか記載がない
- 遺留分について、考慮されていない
- 遺言書を記載したことを誰にもつげなかったため、発見されなかった
- 偽造や、記載時の意思能力を疑われることがある
3.公正証書遺言
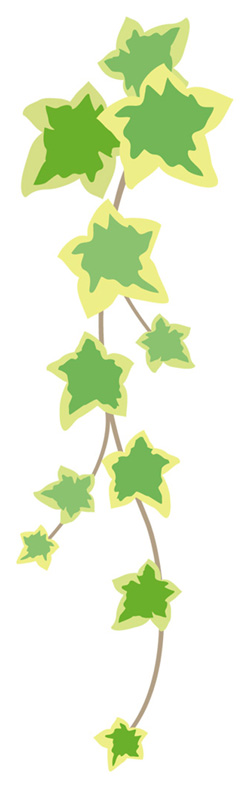
当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています!
公正証書遺言であれば、自筆証書遺言の上記ようなトラブルが発生するリスクは極めて低く、せっかく遺言を書いたにもかかわらず、それがさらにトラブルを生んでしまうという危険を大きく減らすことができます。
公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書になります。証人2名立ち合いのもと、遺言者が公証人に対し遺言内容を口述して作成されます。法律的にも要件の整った正しい遺言書を作成することができます。
